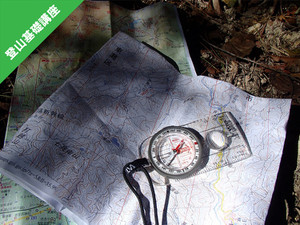こんにちは。好日山荘松本パルコ店です。
先週、浅間山(前掛山、2524m)に天狗温泉浅間山荘から往復で登ってきました。
晴れ。登山口付近は雪が少なく泥の上を歩いたり、凍っている道だったり。徐々に雪の上を歩くようになるが、凍っている所は多い。上の方で登山道を外れない限り全然埋まることはなかった。
一ノ鳥居~二ノ鳥居間の沢沿いルート。右奥に見えるのは不動滝。
不動滝。蛇堀川は赤茶色の川で硫化水素臭がする。
カモシカ平手前から、剣ヶ峰や牙山が見えてくる。
カモシカ平付近から、北八ヶ岳。麦草峠の奥は仙丈ヶ岳?八ヶ岳よりさらに右手の方には中央アルプスが見えた。
カモシカ平から、槍ヶ鞘辺りの岩峰が見えるようになる。
湯ノ平分岐(北側を見て)
湯ノ平分岐から前掛山は見えず。2079m標高点付近の樹林が見えるだけ。湯ノ平分岐~賽ノ河原分岐は樹林。賽ノ河原分岐から10分しないくらいで樹林が開けて一気に前掛山、中央アルプス、第一外輪山などが見える。ここまではほぼ無風だった。
前掛山(第二外輪山)への登り始め
黒斑山
黒斑山は浅間火山の最も古い山体で、約2万4000年前?の噴火、崩壊まで湯ノ平付近に中心火道をもつ標高2800mくらいの成層火山だったらしい。この山体崩壊による岩屑なだれは、北に流れたものは吾妻川、利根川を流れ前橋台地を形成し、南に流れたものは佐久市岩村田へ到達し千曲川を屈曲させた。
第二外輪山を登り始めると冷たい南西風にさらされる。登山道上、踏まれている所は凍っている。
四阿山(左端)、土鍋山、御飯岳、草津白根、横手山、岩菅山、白砂山(右端)
白砂山、谷川岳(中央右、雲かかってる)、武尊山(右端)
鳥居峠、四阿山(中央)、土鍋山、御飯岳(右端)
高妻山(中央左)、焼山、火打、妙高、四阿山
第二外輪山の上に出た所から、前掛山(左奥)
乗鞍岳(左)~白馬岳(右端)。第一外輪山の右側に見切れているのは湯ノ丸山。
シェルター付近から、前掛山(左)。第二外輪山にも噴煙が見える(中央の黒い岩壁の所)。
今まで晴れていたが、シェルター付近にいる頃、南西側から浅間山に雲がかかってきた(2000~2500mくらいの高さで湧いている)。あと30分でも早ければ山頂でもっといい展望が得られたかも。
山頂で雲が晴れないか少し粘ったが指先が冷たくなってきたところで下山。南~東は雲で展望はよくなかったが富士山の頭は見えた。篭ノ登山も湯ノ丸山も桟敷山も村上山も溶岩ドームであり、四阿山、志賀など火山だらけなのがよくわかる景色。
前掛山
前掛山山頂から、釜山の噴煙
どこでも歩けてしまうので第二外輪山からの下り口で下る方向を間違えないように。山頂から下る方向(方角)を少し間違えただけで下に行けば行くほど目的地から遠い所に下り着いてしまいます。
現在、「登り初めは、好日山荘で。」開催中!(1月30日まで)。下記画像リンク参照ください。